「できない」から「一緒にやろう」へ、地域は変わってきた
仙台では診断された本人の入り口から話し合いの居場所、その後の活動(発信、参画)を大切にしています。そのような活動を紹介します
私は宮城県内で多くの仲間たちとともに活動してきました。
診断された直後の不安、孤独、そして将来への心配、そうした気持ちに寄り添い、安心して当事者同士で語り合える場を、地域の中に少しずつ作ってきました。
そして10年前は、宮城県内で認知症の当事者として活動していたのは私ひとりでした。
今ではたくさんの仲間が集まり、50代から90代まで、さまざまな年齢の当事者たちがそれぞれの思いをもって活動しています。
さらに多くのパートナーたちも加わり、みんなで地域を変える力になってきました。
1.診断直後本人と出会える「入り口」
認知症と診断された人が、
その不安を先に乗り越えて前向きに生きる当事者と出会うための、いわば希望とつながる「出会い」の場
(1)おれんじドア
(月1回/東北福祉大学)
(不安を抱えた当事者を同じ経験をした仲間が支えあえる場)
診断されたばかりで不安な人が安心して話せるように同じ立場の当事者が相談にのります
当事者と家族と分かれて当事者同士、家族同士で話し合います
困りごとの話し合いではなく、やりたいことなど話し合いをしています
そこから居場所へつながった当事者がたくさんいます
(2)診療所でのピアサポート(月4回/いずみの杜診療所)
(診察や診断のあとに、当事者同士で気持ちを分かち合える時間)
診断を受けてすぐは不安でいっぱいです。
そんなとき、同じ経験をした仲間がいることが心強い支えとなります
診断後に元気な当事者と不安をもった当事者や家族が出会える事で10年経ってもこんなに元気に生きられるんだと感じる事で笑顔で帰るようになります
病院の中なので医師が診察の予約をピアサポートの日に入れる事で必ず会える仕組みになります
2「安心して話し合える居場所」
当事者同士が集い、何でも気兼ねなく語り合うための、いわば仲間とつながる「語らい」の場
(1)運転免許を考えるつどい
(月1回/いずみの杜診療所)
(まだ運転を続けたい気持ち大切に、やめた時のメリットやデメリットを話し会える場)
免許のことを一人で悩まず、仲間と一緒に話し合いながら考えていく時間です
自分で選ぶ、自分で決める事、説得ではなく納得を大切に応援しています
3〜4回目で自分から返納を決めた当事者もいて家族の安心につながりました
-724x1024.jpg)
(2)仕合せの会
(月1回/仙台市市民サポートセンター)
(当事者だけで自由に安心して語り合える場)
気をつかわず、気軽に話せることが大切で笑いあり、涙ありの大切な時間です
困りごとに対しての工夫や心持ちなどみんなで共有し、自分なりの工夫を生み出します
工夫するようになった事で不安が減り、外出の機会が増えた当事者もいます
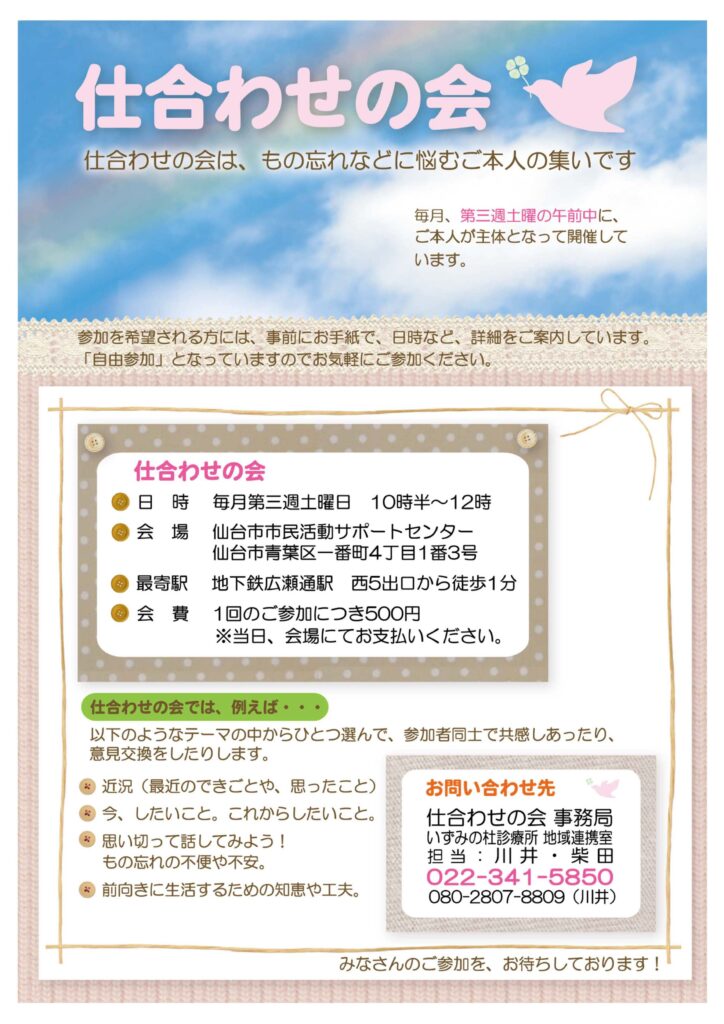
3.本人が社会に「参画」する活動
当事者同士がテーマを絞って語り合い、地域に発信するための、いわば社会とつながる「発信」の場
(1)リカバリーカレッジ(勉強会)
(10~15名でテーマを決めて話し合い、意見を行政に届けます)
私たちの声をカタチにし、地域を少しずつ変えていく場です
最近ではこの場に県や市の人達が「このような施策を考えているけどどう思いますか」と聞きに来てくれるようになりました
話し合いをする事で考え、自分の地域はどうなっているのか、興味をしめし自ら発信するように変わってきました
4.「市や県と一緒に当事者参画の場」
(1)認知症カフェの視察と提言
(宮城県の様々な認知症カフェに訪れて、当事者目線で運営を提案します)
もっと居心地のよい場になるように、参加して一緒に考えます
認知症カフェのチラシに建物の写真や駅やバス停からの地図を入れてほしいと伝えたりしています
ここでも当事者同士が出会い話し合う事で元気になってきた人達もいます。
自分が行きたい居場所はどのような場所なのか当事者自身が考えるように変わり、役割を持つことで、自信を持つように変わってきました。
(2)初期集中支援チーム員として参加
(支援チームの会議に出席し、場合によっては訪問も同行します)
毎月の初期集中チーム員会議にもチーム員として参加して当事者目線から意見を言っています
その事で、会議に参加されている人達が当事者と関係性をいかに結んでいくかを考えるようになってきました
(3)市町村への講演(宮城県からの委託)
(2~3人の当事者がチームを組んで、地域に向けて思いを伝えています)
自分の体験を話することで、地域の理解と支援を広げています
2〜3人でやる事で失敗や体調不良などみんなで補って行う事が出来ます
やればやるほど、話が上手くなっていき、当事者の自信にもつながっています
(4)仙台市の認知症施策の会議に参加
(4人の当事者が、それぞれ違う分野のワーキングに参加しています)
声を届けて、よりよいまちづくりに当事者の意見が反映されるように活動しています
リカバリーカレッジで話し合って考えたことなど、一人一人が会議の場で意見を言うことで会議の中に当事者視点が共有されるようになりました
こうした活動を続けてきた中で、地域や当事者自身が変わってきたことを実感しています。
以前は、「認知症になったら何もできない」と思われていた地域が、今では「一緒に考えよう」と声をかけてくれるようになりました。
そして、認知症に関わってこなかった人達も当事者と一緒に活動するように変わってきたのです。
当事者も最初は忘れることや出来ない事が増える事で落ち込んで自信をなくしていました。
そんな当事者が地域で役割を持って活動するようになると、自信をつけてきて、今では「人のために何かできる事があったらやりたい」「これからも仲間と交流を続けながら一人暮らしを続けてたい」と前向きな言葉を言うように変わってきたのです。
私たち当事者が自分の経験を語ることは、誰かの役にたっているのだと、日々感じています。
認知症と診断されても、自分らしく暮らし続けられる。誰かの役に立ち、社会の一員として生きていける。そんな環境が、少しずつですが地域に根づいてきました。
これからも、地元宮城県の仲間とともに、そして地域とともに、不安をもった当事者が一人でも笑顔になるようにみんなと活動していきたいと思います。


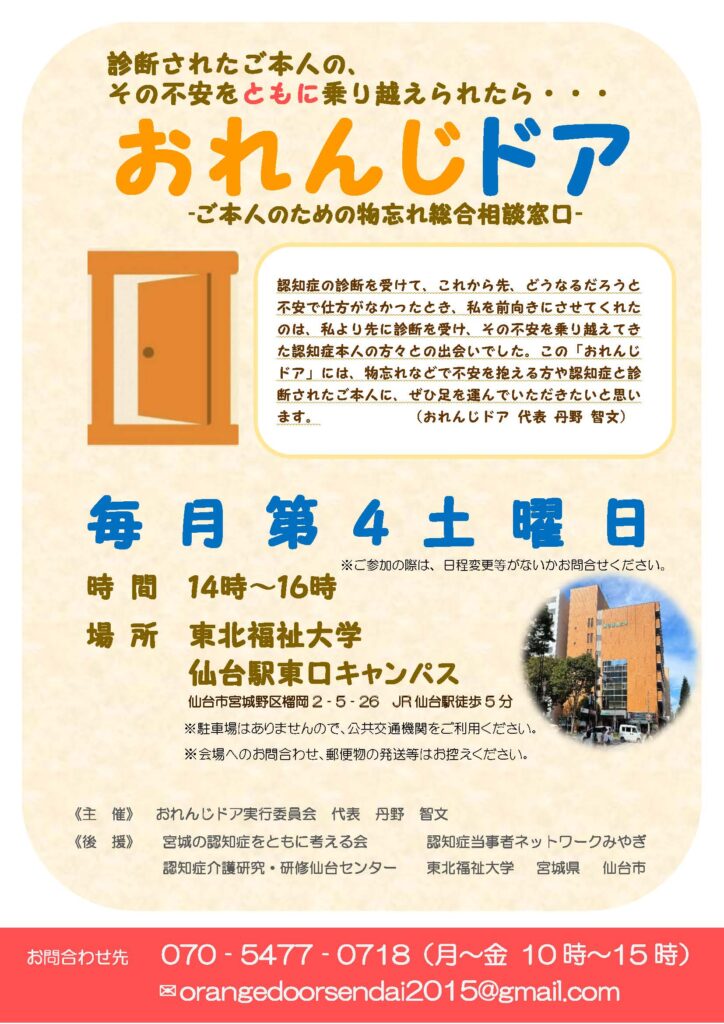


コメント